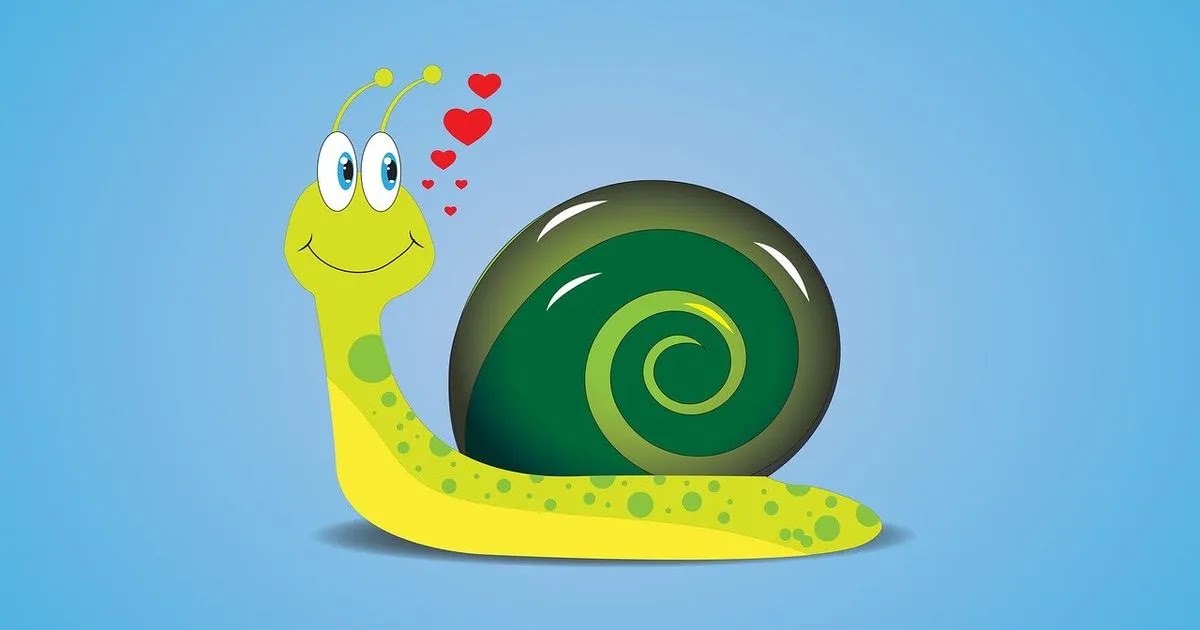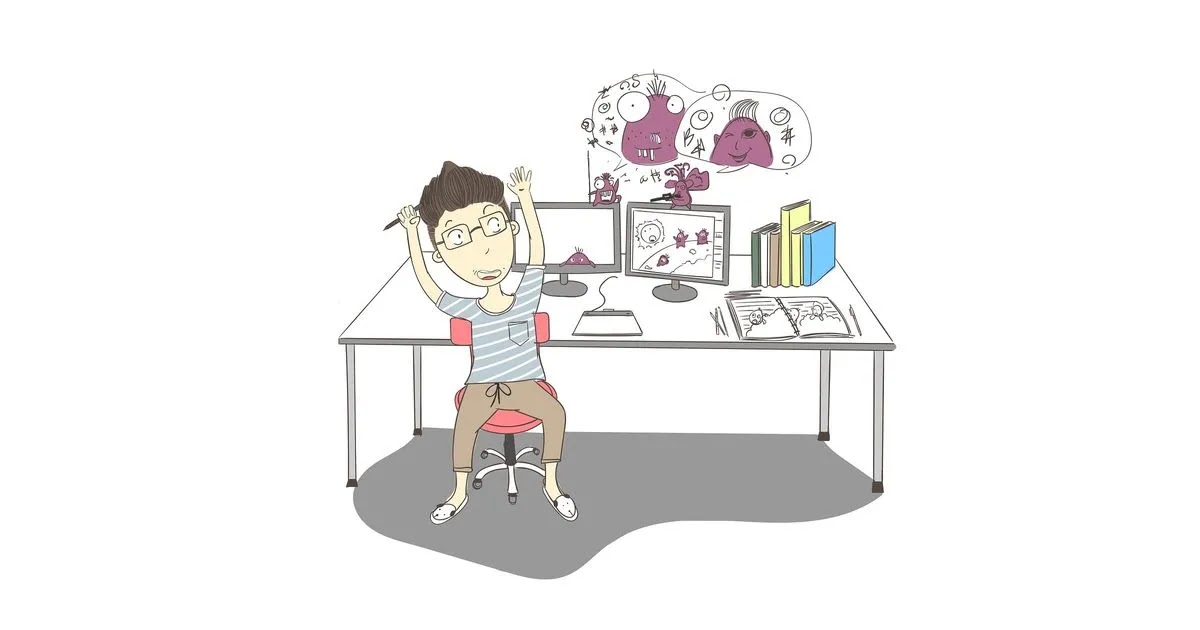【仰天】Google Homeをブランコに乗せる方法 - Part2

はじめに
この記事は2017年10月に発売されたGoogle Homeを改良して楽しむ方法の解説Part2です。
Google Homeは交換用のベースはまだ売ってますが、残念ながら本体は現在発売されてません。
もし、家の中で使われず眠っているのであれば、暇つぶしに改良して遊んでみては如何でしょうか。
おしゃれ雑貨になったGoogle Home
前回の記事でGoogle Homeの音質を改善するプアな実験を紹介しましたが、最後に説明した空中に浮かす構成は見た目や利便性は割り切った方法でした。
バナナスタンドが却下された理由
Google Homeを玉ねぎストックパックに入れて吊り下げる方法は、結局カミさんから好感触を得られず、継続使用の許可は下りませんでした。(涙)
却下された理由は3つです。
1つ目:見た目がいまいちでオシャレでない
袋に入っているとグーちゃんが見えないじゃん!スキンシールを使えなくしてどうするの?
Google Homeはいろいろとカスタマイズ出来るのが売りです。スマホのカバーを着せ替えるのと同じように、お気に入りのスキンシールに衣替えさせる楽しみが無くなってしまいます。
2つ目:Google Homeに触れない
タップで Google Nest デバイスや Google Home デバイスを操作する - Google Nest ヘルプ
タップ操作を使って、Google Nest、Google Home のスピーカーやディスプレイの音量を調整したりメディア再生機能などを操作したりできます。 スピーカ
袋に入っているので「アラームやタイマーの停止」や「音量の調整」ができません。
「OK Google ストップ」「OK Google 音量を4にして」と言えば出来るのですが、たまたま電話中だと出来ませんし、決まりきった操作を毎回音声で指示するのは面倒な場合があります。
3つ目:持ち運びに不便
我が家にはGoogle Homeは1台しかないのすが、カミさんはGoogle Homeを時々別の部屋に持って行って音楽を聴く場合があります。
バナナスタンド毎持って行けばよいのですが、それはちょっと不便だしやりたくない、とのことでした。
これから紹介する方法は以上の問題点を解決したつもりの構成で、何とかギリギリカミさんからも承認をもらった方法です。(笑)
なお、前もってお断りしておきますが、出て来る音は玉ねぎストックパックに入れたものと差ほど変わりません。見栄えが少し良くなった分多少いい感じになったかな、と実感できるレベルです。
100均で手に入るものを利用してますので、お手軽DIYとして遊んで頂ければ幸いです。
本題の説明に入る前にGoogle Homeを空中に浮かす超簡単な技を最初に紹介します。
これを使うとベースの有り無しの差や、最適な高さは何cmかを楽に確認できます。
使用するのは前回紹介したババナスタンドとある道具です。
Google Homeを5秒で空中に浮かす方法
ある道具とは100均で買ったスイング吸盤フックです。

Google Homeの本体重量は477gなので、2倍以上の耐荷重を持つフックを買いました。

使用方法は簡単です。スイング吸盤フックをGoogle Homeの頭に吸着させ、バナナスタンドに引っ掛けるだけです。
センサーの中心より少し上側に取り付けると上手く重心位置に吊り下げることができます。

吊り下げた状態です。

この方法で吊り下げるとベースカバー有無の音質比較も手軽にできるので便利です。
ベースを外した方が音はクリアーになりますが煩く聞こえかも知れません。
この方法のメリットは超簡単に出来る点ですが、デメリットは吸盤をセンサーに直接くっ付けるので、センサーをさわる操作はできません。
また、吸盤フックは吸引面に対して鉛直方向の引っ張り力には弱いので、数十分で外れてしまいます。
短時間の音質チェックにのみご利用して下さい。
どうしてもスイング吸盤フックでしっかり吊るしておきたい方は、はがしやすい両面テープ等で接着固定して下さい。

ナイスタック™ しっかり貼れてはがしやすいタイプ|両面テープ・接着用品|ニチバン株式会社:製品情報サイト
ぴったり技術で明日をつくるニチバンの「ナイスタック™ しっかり貼れてはがしやすいタイプ」ページです。セロテープ®をはじめ、文具、医療用テープ、産業用テープまで。粘着技術を活かして、将来にわたって快適で健康な生活に貢献していきます。
それではカミさんギリギリ公認の新しい方法を紹介します。
使用するの道具はババナスタンドとある小物です。
Google Homeをお洒落に空中に浮かす方法
ある小物とは100均で手に入るコモバスケットミニです。

【楽天市場】イノマタ化学 イノマタ コモバスケットミニ ナチュラル | 価格比較 - 商品価格ナビ
イノマタ コモバスケットミニ ナチュラルの価格比較、最安値比較。【最安値 112円(税込)】【評価:4.52】【口コミ:68件】(12/29時点 - 商品価格ナビ)【製品詳細:ブランド名:イノマタ|ブランド名(カナ):イノマタ】
コモバスケットは小物を整理する便利グッズですが、これを利用する理由は2つあります。
1つ目:サイズと形状
間口Φ11cm、奥Φ10.4cm、深さ11.3cmでGoogle Homeにジャストフィットします。また音が通過できる穴が開いており、左右のハンドルを利用してGoogle Homeを吊るすことができます。
2つ目:材質
コモバスケットの材質は低密度ポリエチレンです。
低密度ポリエチレンはとてもやわらかいので共振しずらく音もビビにくいです。
ハサミやカッターでカットでき穴を広げることも簡単にできます。
またポリエチレン樹脂は体積抵抗率が10^16Ω・cm以上、比誘電率が2.35と優れた絶縁体でスピーカーケーブルの被覆にも使用されてます。
スピーカーユニットをポリエチレン樹脂で囲った場合どのような影響が出るかは未知数ですが電気的特性面で悪さはしないのではと想像してます。
それではコモバスケットにGoogle Homeを入れてみましょう。
コモバスケットの追加工
試しにコモバスケットにGoogle Homeを入れて音を出してみたところ、音が良くなった感じがしませんでした。むしろ若干こもっているような気がします。
コモバスケットにはΦ4の穴が合計216個開いてます。たくさん穴があるのに何故音がこもるのでしょうか。

コモバスケットの材質が原因かと思いましたが根拠となるものは見つかりませんでした。
次に穴の大きさが原因かを確認するため音が通過できる隙間:開口率を計算してみたところ何と16%しかありませんでした。
音の84%は穴の開いてない壁に反射または吸収されるので音がこもってしまうことがわかりました。
そこでコモバスケットの開口率を増やす為に電気ドリルで穴を拡げることにしました。
手持ちのドリルの種類を調べたら鉄鋼用はΦ2~Φ6.5でした。

中ぐりドリルはΦ3~Φ8でした。

穴のピッチは9mmなのであまり大きな穴は開けられませんが手持ちのドリルで何とかなりそうです。
いろいろ考えた結果、Φ6.5とΦ8の穴を互い違いに開けると開口率が52%になることがわかりました。

大小の穴を互い違いに配置したのは2つ狙いがあります。
1つは穴と穴の肉厚を1.5㎜以上確保する為で、もう1つは半径が異なる穴を配置することで穴のエッジで反射する音の拡散効果を高めるためです。
なお、低密度ポリエチレンに穴を開けると髭のようなバリが多く出るので、バリ取りの作業が一番大変でした。
普通のドリルより中ぐりドリルの方がバリは出にくいかも知れません。
ブランコの製作
コモバスケットのハンドルにロープを通して吊るすとロープがGoogle Homeの円形ボディに当たり前後のどちらかに滑ってずれるので水平を保つのが難しいです。
そこでブランコの水平バランスを上手くとる為にヤジロベイの構成にすることにしました。
たまたま木製の空き箱の蓋を捨てずに取っていたので、これを長方形にカットし再利用することにしました。

Google Homeを吊るすロープは可愛さを演出するため、子供のおもちゃのバックに付いていた鎖を再利用することにしました。

切り取った板に鎖を通す穴と吊り中心の穴をドリルで開けます。

鎖を板の穴に通し、ハートのアクセサリーを両側に付けてみました。

コモバスケットのハンドルに鎖のフックをかけババナスタンドに吊り下げて見ます。

何も知らない人がこの入れ物を見ると、可愛いぬいぐるみを入れてしまうかもしれませんね。

さてGoogle Homeを入れる前に少し準備するものがあります。
ベースを外してコモバスケットの中に入れるのですが、そのまま置くのはおススメしません。
前回インシュレーターの効果を説明しましたが、やわらかいポリエチレン樹脂の上にGoogle Homeを直接置くと、音が吸収される恐れがあります。
設置面はしっかりしたものがよいので、木材等の円板の受台をコモバスケットの底に置き、この上にGoogle Homeを載せて下さい。
適当な木材がなければ、コルクシートを円形にカットして受台代わりに使っても結構です。
この時1つだけ注意があります。
ベースを外した状態だと電源プラグの頭が少し出っ張っているため、そのまま受台に載せるときちんと設置できず少し浮いてしまいます。
受台の角を少しザグリましょう。2mmほど削るとプラグの頭は木材と干渉しません。

カッターで削るのは大変なので彫刻刀を使うと便利です。
ではいよいよGoogle Homeをコモバスケットにセットしましょう。
あらかじめ受台をコモバスケットに入れ、電源ケーブルをコモバスケットの穴に通しておいて下さい。

電源ケーブルをGoogle Homeにつなぎ、Google Homeを受台に載せます。
若干アンティークっぽく、オシャレに仕上ったのではないでしょうか。

ブランコを吊っている拡大写真です。

正面の拡大写真です。

電源ケーブルがフリーになっている状態が気になる方は、ケーブルはバナナスタンドの柱にバンドで固定して下さい。

ではPlay Musicで管理人お気に入りのカレン:ソウサさんが歌っているJAZZを流してみましょう。

まあまあの音ですね。デフォルトの音を50点とすると70点くらいでしょうか。
今回アンティーク感をかもし出す為にバナナスタンドとヤジロベイの板は軽く塗装をしました。
その手順を書いておきます。
事前に木材の角はヤスリで少し丸め、表面はサンドペーパで研磨しておきます。
下地の塗料には今回柿しぶを使いました。
失敗しないよう4~5倍に薄め、好みの濃度になるまで何度か重ね塗りします。

柿渋は時間が経過するにつれ化学変化で深い色に変わっていく性質を持っていて長く使えば使うほど味が出てくるので面白いです。
仕上げは100均の水性ニスにしました。

これは塗装前の状態です。

塗装後の状態です。きれいな柿しぶに染まりました。

バナナスタンドの底面に滑り止めのクッションゴムを貼って完成です。

以上で玉ねぎストックパックのリベンジ工作は終わりです。
どうでしょう、楽しんで頂けたでしょうか。
今後
自己採点で甘めに70点を付けましたが80点に近い構成を新たに試作中です。
上手く出来たらブログで報告する予定です。
あまり期待せず待っていて下さい。(誰も期待してないか。。。)
追記
第三弾のアイデアの追加部品を探索する為、100均ショップ巡りをしました。
するとあるお店でコモバスケットミニのピュアホワイトを見つけてしまいました。

本体と同じ色に合わせるとどんな感じになるのか見て見たくなり、思わず衝動買いしてしまいました。
100円(税抜き)だからと言っていい気になって小物を買っていると、気づいたら1000円を超える時があります。しかも、買った後使わず数年オブジェになり、最後は置場がなくなり粗大ゴミになる場合があり要注意です。
そうならないように、速攻でドリルで穴を拡げる加工をしました。

加工前(内側)

加工後(内側)

加工前(外側)

加工後(外側)

開けた穴の大きさはΦ8とΦ6です。Φ6.5にしなかったのは全部穴グリドリルを使ったためです。開口率は48%に下がりますが、4%の違いは分からないだろうと割り切りました。
穴を拡げたところピュアホワイトはナチュラルに比べバリが目立ちますね。
カッターの刃先でちまちまバリを取っていると時間がかかるので、シャーシリーマを使ってみました。

簡単なバリはすぐ取れますが、力を入れすぎると削ってしまって逆にバリが出てしまいました。これではいたちごっこです。(汗)
実験なのでバリ取りは適当なところで止め、Google Homeを入れてみました。

うーん、微妙な感じですね。何だか安っぽくなった気がします。(100均を使っているので事実ですが。。。)
音については差は感じられませんでした。
今試作している第3段弾の構成の方が、もっとカッコイイ気がします。
今月中には完成するよう頑張ろうと思い、今ビールを飲みながら構想を練っています。
気軽に足跡残してね!
この記事が「気になった・参考になった」と感じた方は、リアクションボタンか、ツイッターで♡いいねを押して、足跡を残して頂けると嬉しいです。
https://t.co/1Yr3iySCD4
— heavy-peat (@AfterWork_Lab) July 25, 2021
Google Homeをブランコに乗せての音を良くする方法の解説をリライトしました。
Google Homeを吊ってみたい方は参考にして下さい。#GoogleHome #SmartSpeker
それでは今回の記事はこれでおしまい。