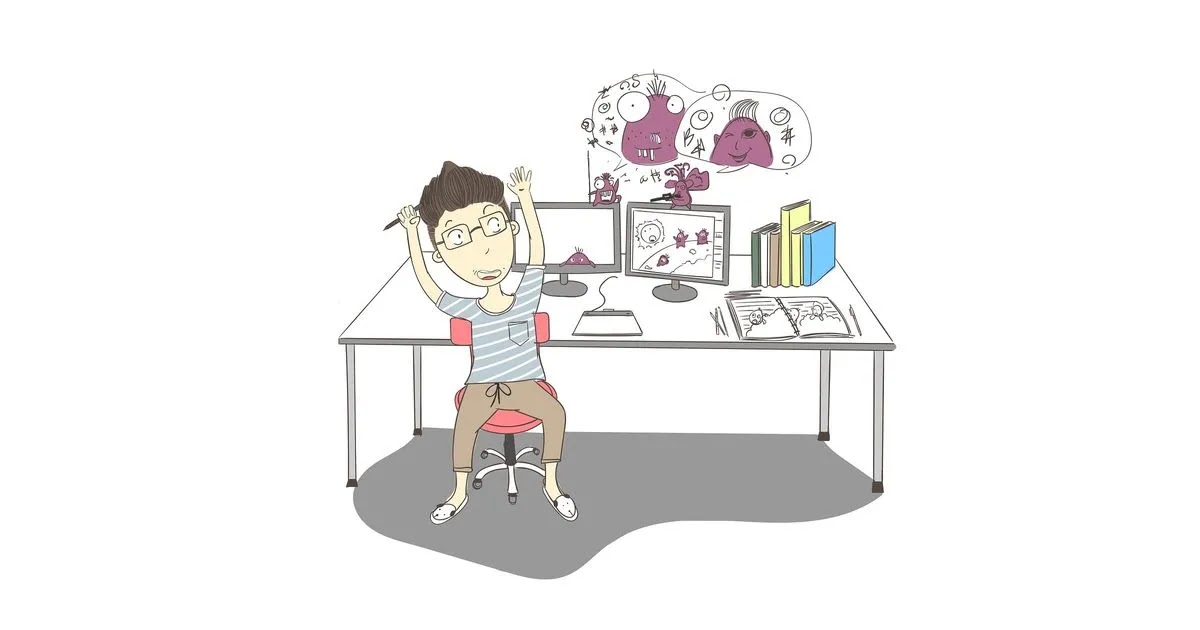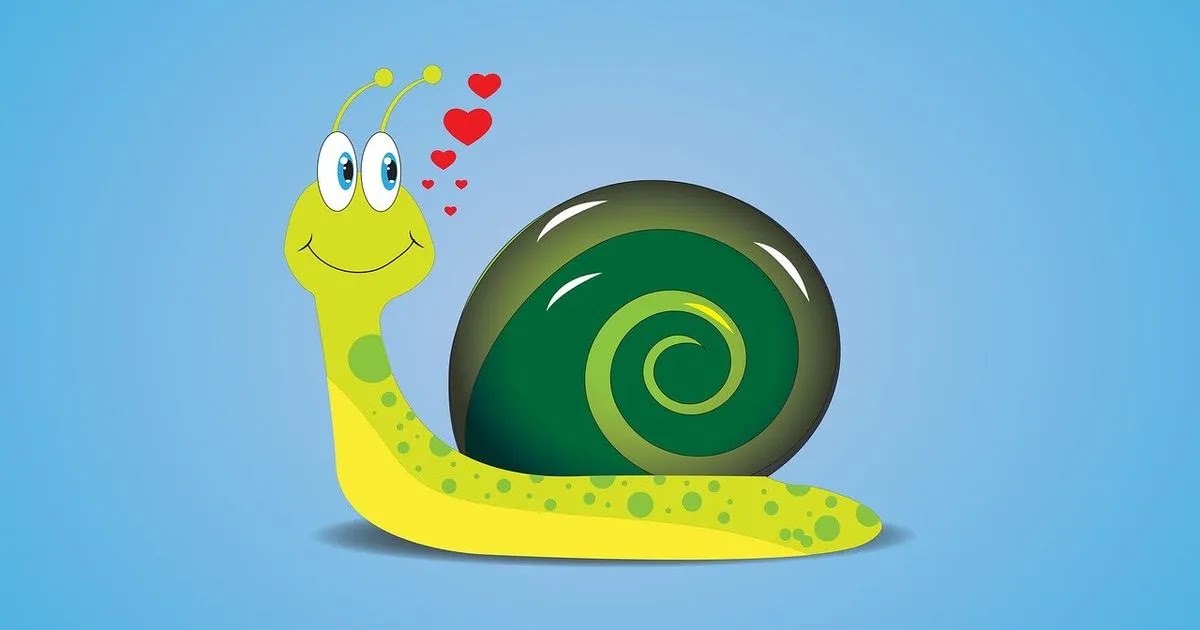【激変】Google Homeのベースを魔改造する方法 - Part3

はじめに
この記事は2017年10月に発売されたGoogle Homeのベースをある物と交換して音を良くする方法を解説したものです。
Google Homeのベースに不満を持っている方は、暇つぶしに改良して遊んでみては如何でしょうか。
Google Homeの音と見た目の両方を格段にドレスアップできたので、その方法を公開します。
お断り
もしGoogle Homeの上半身をドレスアップする為にスキンシールを探しに来られた方は、ここにでは見つからないので下記サイトでお探し下さい。
楽天ではたくさんの種類のスキンシールが安く販売されてます。きっとあなたにピッタリのスキンシールが見つかると思います。
本体以外にアダプター用もセットとなっているので非常にお得です。

もし下半身をドレスアップする為に純正のベースをお探しの方はGoogle ストアでBase for Google Homeをご購入下さい。
Base for Google Home - Google Store
Interchangeable metal and fabric bases bases let you customize your Google Home so it blends into your home’s decor.
ファブリック製だとコーラル、金属製はカッパーとカーボンが選択できます。

なおスキンシールを貼ったり、違う純正ベースに交換すると気分は変わりますが音質は変わりません。
音がマシになるベースをお探しでしたら残念ながら現時点で販売されておりません。
しかし、このブログを訪問された方は非常にラッキー!です。
100均のある素材を利用すると、えっ!マジ!嘘!とつぶやけるくらい、たぶんスタイリッシュに変身し、音もクリアーになるかもしれないベースを自作することができます。
要領さえ分かれば1~2時間で誰でも簡単に作れるので、興味がある方は是非遊んでみては如何でしょうか。
ベースをカスタマイズしよう
これから紹介するのはGoogle Homeのベースをオリジナルのベースにカスタマイズすることで、音質と見た目を変える方法です。
なぜベースを変えるのか?
理由は2つあります。
1つ目はオリジナルのベースは音を濁しているからです。
これは後で詳しく説明します。
二つ目はベースのおしりが丸いことです。
どこが気になるかと言うと、何となーく丸いおしりにショーツやブルマを被せているように見えるのです。
決しておしりが嫌いな訳ではありません。
(いや大好きな訳でもありません)
誤解されるので言い換えますが、Google Homeが何となーく起き上がり小法師に見えるのです。
何を言いたかったかというと「あまりカッコ良くはない」ということです。
金属製のベースは高級感がありますが、セクシーなスキンシールを貼っていると貞操帯に見えるかもしれませんね。(笑)

【楽天市場】Google Home 専用スキンシール グーグルホーム スマートスピーカー カバー ケース フィルム ステッカー アクセサリー 保護 011550 おしゃれ 女性 セクシー:e-Mart
Google Home 専用 貼るだけ簡単 オシャレなデザインスキンシール。Google Home 専用スキンシール グーグルホーム スマートスピーカー カバー ケース フィルム ステッカー アクセサリー 保護 011550 おしゃれ 女性 セクシー
さて、おふざけはここまでにして一つ目の理由について詳しく説明します。
オリジナルのベースはどこがマズイの?
結論を先に言うと、音が通過する穴の面積:開口率が低すぎるのです。
オリジナルのベースは内側はポリカーボネイト製(PC:通称ポリカ)のカバーでハニカム形状の穴が無数に開いてます。
ポリカはプラスチックの中で最高レベルの強度(ABSの5倍)を持ってますので、Google Homeを机の上から落としても容易には壊れません。
下の模式図は6角形の穴とリブの寸法を描いたものです。音が通過する穴の面積は音が反射する壁の面積より十分に多いように見えます。
本当なのか検証してみましょう。
きちんと計算するとベースの内側の開口率は51%でした。
言い換えると49%は壁で音の通過の障害物になっているのです。

なお、スピーカーを保護するサランネットの開口率は50%前後なのであまり驚く必要はありません。一般的なのでご安心下さい。
但し、ポリカは内部損失が高い材料なので高音は吸収されませんが、逆に音が反射し戻ってくるので、音の濁りの原因になっている可能性があります。
これは余談で少し補足します。
次にベースの外側を見てみましょう。
ベースの外側はナイロン 33%、ポリエステル 67%のファブリック製のカバーが接着されてます。
下の画像はベースの内側をiPhoneで撮ったものです。

光が沢山見えるのでファブリックの繊維密度は低く、音が通過できる隙間が十分あるように見えますが、実は錯覚です。
これは光が回折効果で回り込んでいるので、隙間が広く見えているのです。

音も波なので回折するのですが、スピーカーから出た低音は外側に回り込みます。
詳しく知りたい方は下記ブログをご覧下さい。

【簡単】Google Homeの音を良くする方法 - Part1 - after work lab
はじめに この記事は2017年10月に発売されたGoogle Homeを改良して楽しむ方法を解説したものです。 Google Homeは現在発売されてませんが、家の中で使われず眠っているのであれば、暇つぶしに改良して遊んでみては如何でしょうか。
ではファブリック製のカバーの開口率はいくつなのでしょうか。
管理人は顕微鏡を持ってないので、年賀状を印刷しているMFP(マルチ・ファンクション・プリンター)でベースをスキャンしてみました。

光学解像度は2400dpi×4800dpi(主走査×副走査)ですが、標準ソフトでは最大600dpi(42μm)の解像度でした。
下の写真はdot by dotの画像で表示したものです。
ナイロンやポリエステルの繊維の太さは約1d(デニール):約10μmくらいなので、600dpiでは細かい繊維を確認することができません。

この画像で確認できるのは繊維を数百本束ねた糸の形状が分かる程度でした。
もっと高解像度で読み込めないか調べたら、ScanGearというソフトの拡張モードで1200dpiで読み取り可能でした。さっそく裏技を使ってスキャンしてみました。
今度は糸の形はクッキリ分かるようになりました。
(画像をクリックすると差がよくわかります)

しかし、イメージセンサーはコストダウンされた安いCSI方式(Contact Image Sensor)なので写りはあまり良くないですね。
しかも、画像左側にセンサーチップのつなぎ目が主走査方向に縦スジとしてクッキリ表れてます。
メーカはなぜCSI方式の解像度を600dpiに制限しているのか理由がわかった気がします。
実売価格1万ちょとのMFPで高解像度でスキャン出来ると、クレームが殺到するからでしょうね。
CDD方式(Charge Coupled Devices)だったら焦点深度が深いので左右がボケは少なく、つなぎ目は発生しないはずです。
ちなみに一番最初に買ったMFPはPIXUS MP950でスキャナーはCCD方式(3200dpi × 6400dpi)でした。
8年使用で重送が多発し年賀状が多量に無駄になったので、PIXUS MG6330に買い換えました。
MGシリーズからスキャナーはCCD方式からCSI方式に変更され、インクも互換性が無くなっていて無駄になり、ダブルでガッカリした記憶があります。
そしてお決まりのようにPIXUS MG6330は3年使用でどうやってもインクが出なくなり、また買換えとなりました。
今度はインクの互換性がない最新機種は選択せず、型落ち品のPIXUS MG7530に買い替えました。(現在使用中)
ソニータイマーという言葉がありますが、インクタイマーというのも確実に存在しており、コストと品質はずっとアンバランスな状況です。
本件とは関係ない愚痴はここまでとし、画像の詳細を観察してみます。
Google Homeのファブリックで使用されている生地ですが、画像で判断すると天竺編みまたはメリアス編みと言われる横編みに似てます。
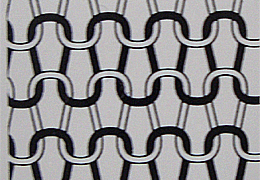
ニットの基礎知識:丸編みの基本編地 | 縫製工場ミヤモリは年間100万枚超の生産力のアパレル専門OEM生産縫製メーカーです
天竺(てんじく)編、フライス編、スムース編の基本
細い繊維がポリエステルで、太い繊維がナイロンでしょうか。
隙間は少なそうですが、立体的に編まれているので、ファブリックの開口率はざっくり40%~50%くらいでしょう。

以上よりオリジナルベースの開口率は内側のカバーと外側のファブリックの開口率を掛け合わせて、20%~26%と推定されます。

中間まとめ
オリジナルのベースではスピーカーユニットから出た音の74%~80%は反射または収音の影響を受ける為、濁ってこもった音に変化すると思われます。
スマホのカバーを着せ替える感覚で、色違い・材質違いのベースに3000円~を投資するのは問題ありませんが、音質も向上するのでは、と勘違いして買うとガッカリするので気を付けて下さい。
それでは、本題のベースのカスタマイズ方法について説明します。
ベースのカスタマイズ方法
どんなベースにカスタマイズするのか。
第一に優先するのはデザインです。
どんなに音が良くなってもカミさんがOKを出さなければ、Google Homeをリビングに置くことはできません。
見た目を犠牲にした音質向上はNGです。
こんなにハードルを上げて大丈夫?と心配されるかも知れませんが、実はスタイリッシュなデザインと音質向上の両方を実現できる素材を100均で見つけたのです。
それは一体何でしょうか?
・・・
・・・
・・・
・・・
答は排水口のゴミキャッチャー(ゴミキャッチ)です。

ゴミキャッチャーで何でスタイリッシュになるの?ご冗談でしょう!と思われるかも知れませんが、実はこれが大化けするのです。
ゴミキャッチャーをベースの素材にした理由は2つあります。
第1は開口の大きさです。
ベースにするものは音が通過する開口が必要ですが、リブの厚みとスリット(開口)の幅は約1.5mmとなっていて、開口率は50%前後あります。
穴を拡げなくても使用できる可能性が高いです。
第2は材質です。
ゴミキャッチャーの材質はポリプロピレン樹脂(通称PP)です。
ポリプロピレン樹脂は耐熱温度が100℃~140℃で機械的強度も高い材質です。
Google Homeを10個載せても潰れることはありません。
ベースに使っても問題ないと思います。
ではさっそく製作方法を説明します。
ゴミキャッチャーはいろんな種類がありますが、"あトん"が購入したのは山田化学製とサナダ精工製の2種類です。色はホワイトで底はフラットな形状を選択しました。

【楽天市場】山田化学 山田 排水口ゴミキャッチャー | 価格比較 - 商品価格ナビ
山田 排水口ゴミキャッチャーの価格比較、最安値比較。【最安値 110円(税込)】【評価:5.00】【口コミ:2件】(12/29時点 - 商品価格ナビ)【製品詳細:ブランド名:山田|ブランド名(カナ):ヤマダ】

流し用ゴミキャッチ - (キッチン|シンク用品):サナダ精工株式会社
流し用ゴミキャッチ - (キッチン|シンク用品):サナダ精工株式会社は、プラスチック家庭用品の開発型メーカです

2種類購入した理由は開口幅と全高が違うからです。
開口幅:山田化学製(1.2mm~1.35mm)< サナダ精工製(1.45mm~1.6mm)
全高:山田化学製(70cm)> サナダ精工製(59cm)
ではGoogle Homeのベースを外してゴミキャッチャーに入れてみましょう。
ちょうどいい感じにすっぽりと入ります。

試しにちょっと音を出してみて下さい。オリジナルベースより音はクリアーになっていることに気づくと思います。
これで十分と思った方はここで作業終了です。お疲れさまでした。
と言うのは冗談で、本当の使い方は上下逆です。
ゴミキャッチャーの底に穴を開けGoogle Homeを挿入するのです。
えー!本当に入るの?と疑問に思われるかも知れません。
写真を見た頂くとわかりますが、Google Homeのベースの外径とゴミキャッチャーの底の外径は偶然ピッタリ同じなので大丈夫です。

実は山田化学のゴミキャッチャーは年明けに発見してました。しかし、茶殻が入った緑色しか在庫が無かったので購入はスルーしてました。
しかし、2月上旬にホワイトが入荷していたのに気づき、無くなる前に速攻で買いました。(笑)
そして別のお店にも無いか100均巡りをしたところ、サナダ精工のゴミキャッチを見つけました。
底に穴を開ける
Google Homeを挿入する為にはゴミキャッチャーの底を取り除き穴を開ける必要があります。
では刃が厚い大き目のカッターを用意して下さい。

いっきに円形にカットしようとすると失敗する恐れがあるので、数回に分けて穴を開けて行きます。
まず、大雑把に四角にカットしましょう。
次に内側に残った三日月状のリブをカットして下さい。


最後にエッジがでこぼこしているので基本肉厚が残こるようにカットします。
カッターでは上手くカットできないので、平刃の彫刻刀を使うことをおススメします。

彫刻刀を穴の内面に沿って滑って下して行き、基本肉厚が残こるように少しづつ押し切って行きます。

写真では分かりづらいので模式図も載せておきます。

若干大変な作業ですが、この部分が綺麗にカットできないとGoogle Homeを載せた時隙間が出来てしまいます。焦らず慎重に行って下さい。
底のカットが終了しました。お疲れさまでした。

ベースを外したGoogle Homeの内径はΦ86㎜です。Φ87㎜±0.5㎜の穴に仕上がるとガタつきも少なくピッタリ収まります。
多少エッジがデコボコしてますが、Google Homeを載せたらエッジは隠れて見えなくなります。
ではGoogle Homeを載せてみましょう。上手くピッタリ収まりました。

では音を出して見ましょう。特にビビリもなく問題はありません。
気にならなければしばらくこの状態で使っても良いのですが、電源ケーブルの引き回しが上手く出来ないので、最後にフランジをカットします。
フランジの削除
フランジのカットは底のカットより楽です。
まずフランジの根元にカッターの刃を当て、円周方向に切れ込みを入れて行きます。一気にカットしようとすると失敗したり、滑って手を切ってしまう恐れがあるので止めましょう。
2~3周カッターの刃で切れ込みを入れたら、大型のハサミで切っていきます。
管理人は昔ホームセンターで買った498円のステンレス万能ハサミを使いました。


このハサミは分厚いいダンボールを資源ゴミに出す時に使用してますが、0.5㎜の板金もカットできるハサミです。
なお、ニッパでカットするのはおススメしません。切断面がギザギザになるので止めたほうが良いです。キッチンの万能ハサミもこの用途には適さないので無理な使用は避けましょう。
万能ハサミが無い場合は、カッターで更に5~6周切れ込みを入れると、上手く切れると思います。
カット完了後のゴミキャッチャーです。右が山田化学製、左がサナダ精工製です。
フランジが無くなりスッキリしました。

次に電源ケーブルを通す溝を作ります。彫刻刀を使うと簡単にカットできます。

これで一応終わりなのですがフランジの切断面がデコボコしているのが少し気になります。
この部分はドレスアップしてごまかすことにします。
ドレスアップの方法
用意するのは自動車のドアモールです。管理人が使ったのは余剰品で、余ったドアモールを捨てずとっておいたものです。

適当な長さにカットしておきます。

ドアモールが無ければ、マスキングテープでエッジをカバーしても大丈夫です。
ではドアモールの取り付け方を説明します。
ドアモールをゴミキャッチャーのエッジに圧入するのですが、しばらく放置してると滑って抜けて来ます。

抜けにくくなるようポリプロピレン用の接着剤を塗って固定します。

上に重りを載せ1時間ほどで接着完了です。

ドアモールの装着が完了しオリジナルベースの完成です。パチ!パチ!
山田化学製のオリジナルベースです。

オリジナルベース装着状態

サナダ精工製のオリジナルベースです。

オリジナルベース装着状態

シルエットがLINEのClova WAVEに少し似てますが、気にしないで下さい。

まだこれで終了ではありません。最後の仕上げがあります。
「グーグルホームの音を良くする方法」で解説した内容を思い出して下さい。
スピーカーはテーブルに直置きせず、4cm~6cm持ち上げた方が良いのです。
Google Homeをひな壇に上げる
3月3日はひな祭りでした。
せっかくなのでGoogle Homeをおしゃれな台に置いてあげましょう。
ただし、ゴミキャッチャーで作ったオリジナルのベースは底面が全面開口なので、これを台に載せるには一工夫が必要です。
皆さんはこの課題にどう対応しますか?
方法1 高さ3cm~4cmのブロックの真上にGoogle Homeを載せる。
→これは×です。オリジナルのベースが脱落するので意味がありません。
方法2 高さ3cm~4cmのブロックをオリジナルのベースの下に置く
→これは△です。不安定です。音量を上げるとズレて脱落するでしょう。
方法3 オリジナルのベースの下をワイヤークリップで持ち上げる
→これは△です。何となく良さそうですが少し強度不足ですね。
管理人が考えた方法はエコー金属の「ワイヤーウッドフラワースタンド」の利用です。

このスタンドの直径は実はゴミキャッチャーの開口とほぼ同じ110㎜なのです。
ただし、このままの状態では使いません。
裏側のネジを外して円盤を取り除きます。


円盤を外す理由は音を良くする為です。
ベースを風通しが良いスカート?に変えたのですから、音の抜けを良くする為に設置面は塞ぐべきではありません。
でも、板を取ったらワイヤーの上に乗っかる状態になってしまいます。
ズレ落ちてしまうのでは?と心配になるかも知れませんが大丈夫です。
「ワイヤーウッドフラワースタンド」には円盤を固定している長方形の突起が3つあるのでこれを利用します。
ではこの突起をペンチで88°~89°に曲げ起こして下さい。

ワイヤーウッドフラワースタンドをゴミキャッチャーの中に入れます。

写真に示すように、曲げ起こした3カ所の突起が、ゴミキャッチャーの抜け防止ガイドとして利用できるのです。
最後にこの中にGoogle Homeを挿入したら完成です。パチ!パチ!
山田化学製ゴミキャッチャー + フラワースタンド

サナダ精工製ゴミキャッチ + フラワースタンド

後ろはこんな感じです。

では本格的に音を出して見ましょう。
狙い通り音の抜けが大変良くなりました。大成功です。
たぶん見た目も悪くありません。(まだこの時点では自信度70%)
最終ゴールはカミさんのOKです。
恐る恐るカミさんに見せたら「えっ!これ何?パパが作ったの?どうやったの?」と一応肯定的な反応でした。(安心)
音質評価
では音質がどれくらい変わったのか、管理人の駄耳で比較テストしたいと思います。
テスト順番
①オリジナル

②ベースを外し高さ4cmの木製台に設置

③山田化学製ゴミキャッチャー+フラワースタンド

④サナダ精工製+フラワースタンド

評価項目
次の4つの項目、音もこもり、音のにごり、音のうるささ、クリアーな低音について確認しました。
試聴に使った音は2曲です。
ボーカルの評価にShawn Mendesの「Treat You Better」、中低音の評価にRihannaの「Phresh Out The Runway」を再生します。


評価結果
(左側:不利 右側:有利)
音もこもり ①>②=③=④
音のにごり ①<③=④<②
音のうるささ ②>③=④>①
低音はクリアーか ①<②<③<④
②がベストだと思っていたら、④が僅差でベターな感じです。
一番違った部分は低音の出方でした。
クリアーで迫力がある中低音が出て来るとは思いませんでした。
なお、壁に近づけると更に中低音が豊かになります。
イコライザーで低音は-6dbに下げ、壁から20cm離すとバランスが取れました。
今はBOSEのスピーカーの横に置いてますが、何も知らない人はたぶんBOSEから音が出ていると勘違いすると思います。

まとめ
たった200円(税抜き)でここまで激変するとは予想しませんでした。
偶然とは言え100均は良い素材が眠っているお宝の場所ですね。
皆さんも気分転換に自作しては如何でしょうか。
我が家のオリジナルベースは箱に戻し、しばらくお休みとなりました。

ここまで音がまともになると、早くステレオ化したいですね。
余談
純正のベースはなぜ100均のゴミキャッチャーに負けてしまうのでしょうか。
開口率の低さ以外に、どんな原因があるのか考察してみました。
純正ベースの不利な点
ポリカ製のベースの形状を細かく見ていくと音質に不利な部分がいくつか目に付きます。
ブログの前半でベースの内側は49%が壁になっていると説明しましたが、この壁が円周方向の平面なので壁に反射した音は180°跳ね返ってスピーカーユニットに戻ってくることになります。

もう一つ気になる点は6角穴の抜き方向です。図を見て分かるように6角穴は上下左右の4方向スライドで抜かれてます。

従って穴の溝の方向も上下左右に向いてます。スピーカーユニットから出た音は音波として拡散するのですが、6角穴を空気の通り道である短いダクトと見立てると、音はダクトと平行な方向に進みます。
スピーカーユニットに垂直に穴が開いているから別に問題ないんじゃないの?と思われるかも知れませんが、指向性が高くなるので、広がり感が少なくなります。
ファブリック製のカバーをベースに被せたのは指向性を減らし、うるささを和らげる為なのでは、と思います。
ではゴミキャッチャーはなぜ音が良いのでしょうか。
ゴミキャッチャーの有利な点
それはリブの形状と穴の方向に秘密があります。
内側のリブの先端に着目して下さい。
角が半円になっていて半径方向に放射状に配置されていることに気づくと思います。

これは金型への喰いつきを少なくし離型時の抜き抵抗を少なくする為ですが、別の効果もあります。
リブの先端が半円になっているので水の流れをガイドしスムースに排出する効果が期待できます。
これは音の伝搬もいっしょです。
先端が半円なのでリブに当たった音は中心には戻りません。180°の範囲で拡散するので、特定の周波数で音が濁ってこもることが少なくなると思われます。

また、開口の溝は半径方向に向いているので、スピーカーユニットから出た音の一部は半径方向に広がります。
ミニ音響レンズのような効果があり、若干聴きやすい音になると思います。
しかし、Google Homeのベースの金型はコストが高く、多数個取りが難しいスライド構成にしたのでしょうか。
材料はポリカで穴の形はハニカム形状で強度が高いのだから、リブの肉厚は0.8㎜~1mmまで細くするか、ハニカムのピッチを拡げ、開口率を大きくすべきだったのではと思います。(余計なお世話か)
ゴミキャッチャーどちらが良いベースなの
山田化学製とサナダ精工製はどちらが良いベースなのでしょうか。
音での評価はサナダ精工製でした。部品として評価するとサナダ精工製の方が、精度よく作られているように見えます。
あえて理由を上げるなら外観で差がありました。
フランジを比較するとサナダ精工製の方がヒケが少ないです。また四角穴のメッシュもバリが少なくきれいです。
どちらも1点のピンゲートで射出成形されてますが、ゲート跡もサナダ精工製の方がきれいです。
要は金型の射出圧力、型締め力、金型の温度、成形温度がきちんとコントロールされている証拠です。
100均の商品とは言え、サナダ精工は品質管理をきちんとやっているメーカと推測されます。
なお、管理人が購入したロットがたまたまこのような差があったかも知れませんので、ご了承下さい。
このブログを見て自作しようと思っている方は、現物を見て判断した方が良いと思います。
最後に、バナナスタンドはどうするの?と気になっている人がいるかも知れません。
結論から言うと、今回試作したオリジナルベースは空中に浮かしたりはしません。
理由は単純で、上手く吊るせないからです。
フラワースタンドのリングに紐を通して吊りたいところですが、吊り位置がGoogle Homeの重心よりかなり下の位置なので、バランスを取るのが非常に難しいのです。
例えて言うと、ブランコに鎖を握らず立っている状態を想像して下さい。
ちょっと重心がズレると落ちてしまうことが想像できると思います。
この記事が「気になった・参考になった」と感じた方は、リアクションボタンか、ツイッターで♡いいねを押して、足跡を残して頂けると嬉しいです。
https://t.co/FgV3u8whov
— heavy-peat (@AfterWork_Lab) July 25, 2021
Google Homeのベースを別物に交換して音を良くする方法の解説をリライトしました。
Google Homeで遊びたい方は参考にして下さい。#GoogleHome #SmartSpeker
それでは今回の記事はこれでおしまい。